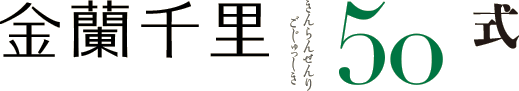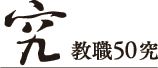『無名抄』は「数奇(すき)」と呼ばれる、和歌に偏執する人々の説話を多く載せる。
秀歌一首を得るために寿命の五年を賭けたという頼実、
九十歳になってもまめまめしく歌会に出席したという道因、
ひたむきな詠作三昧で若死にした女流歌人宮内卿…
彼らの姿は見ようによっては常軌を逸した「烏滸(をこ)」と見えなくもない。
たしかに、
九十ばかりになりては、耳などもおぼろなりけるにや、会の時には、ことさらに
講師の座に分け寄りて、脇もとにつぶとそひゐて、みづはさせる姿に耳を傾けつつ、
他事なく聞ける気色など、なほざりの事と見えざりけり。
(道因は九十才ばかりになってからは、耳なども遠くなったのだろうか、
歌の会の時には、ことさらに講師の座に人をかき分け近寄って、講師の
すぐ脇にぴたりとくっついゐて座って、ひどく年老いた姿で耳を傾けながら、
余念なく講師の言葉を聞いていた様子などは、並大抵の事とは見えなかったものだ。)
という件を読むと、道因の滑稽な姿に「そこまでするか」と思わす失笑してしまう。
しかし、その一方で「そこまでやってのける」道因に頭が下がる思いもある。彼らの姿は一様にひたむきで、真摯で、和歌への強い情熱が常軌を逸脱するほどの行動となったのだろう。作者の長明もそんな彼らにいたく共感し、多くの「数奇者」の姿を『無名抄』に書き留めたのだろう。
同じく長明の著作に、『発心集』という説話集がある。『発心集』という書名が示す通り往生できたか否かより、いかにして往生につながる「発心」を持続し得たかどうかを長明は重要と見ているようだ。「発心」を持続させるものが、数奇者の情熱でもあるのだろう。
これらの説話に描かれた数奇者を思う時、ともすれば惰性に流され、知らず知らずのうちに怠惰に陥りがちな我が身を戒めつつ、「好き」という情熱を失わずにいたいと思う。